 コト助くん
コト助くん
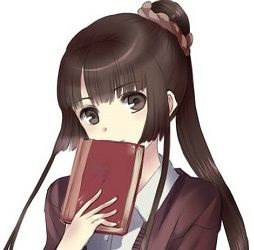 コトハちゃん
コトハちゃん
 コト助くん
コト助くん
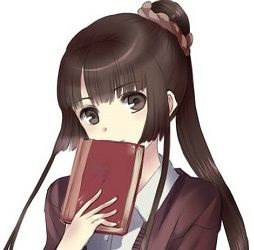 コトハちゃん
コトハちゃん
さて、日本の古い文献でも名前が出てくる「鬼灯」という花。
この鬼灯の花言葉には、怖い意味と良い意味があるけど、その由来を知ると結構面白いんですよ!
それに歴史を見ると名前が違ってたりしますからね〜。
というわけで今回は、鬼灯の花言葉の良い・悪い意味別や、その花言葉と花名の由来をご紹介しているので、ぜひ参考にしてください!
鬼灯の花言葉

鬼灯(ほおずき)って、名前からして「鬼(おに)の灯(ともり)」と怖そうな印象です。
一体どんな花言葉なのでしょうか。
まずは、比較的に良い意味からチェックしていきましょう!
鬼灯の良い花言葉は、
- 心の平安
- 不思議
- 自然美
- 私を誘ってください
となっています。
「あれ?そんな良い意味じゃないね!」
と思ったかもしれません。
まぁ、このサイトでも花言葉を色々書いていたので、他の花に比べると良い意味とは言えないんですよ。
なので、あくまで悪い意味と比較しての話で、それほど鬼灯の花言葉は、悪い意味が多いというわけです。
さて、以上が鬼灯の花言葉の中で比較的に良い意味になります。
冒頭でもお伝えした通り、鬼灯には「悪い・怖い意味の花言葉」が多くあるんですよ。
なので次は、鬼灯の怖い花言葉を一緒に見ていきましょう!
鬼灯の怖い花言葉って?
鬼灯の怖い花言葉は、
- 偽り
- ごまかし
- 欺瞞(ぎまん)
- 半信半疑
- 偽りの恋
- 浮気
- 不貞
※欺瞞…人の目を騙して、あざむく事
どうですかー?
鬼という名前が入ってるから、もっと凶悪な花言葉と思った人もいるかと思いますが、詐欺師って感じですね。
または、チャラ男って言ってもアリかもです。笑
ちなみに、西洋での花言葉は英語では、
- deception(ごまかし)
という花言葉になります。
海外でも鬼灯には、ウソの花ってイメージがあるみたいですね〜。
 コト助くん
コト助くん
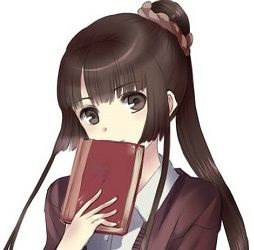 コトハちゃん
コトハちゃん
 コト助くん
コト助くん
花言葉ってロマンチックだったり、素敵な言葉が多い印象ですよね。
でも、鬼灯の花言葉は「詐欺師や狼少年」のような、ウソを表される言葉が付けられていました。
しかし、「何故、こんな悪い意味になったか?」って気になりませんか?
せっかくなので次は、鬼灯の花言葉の由来を詳しく掘り下げでいきたいと思います。
鬼灯の花言葉の由来と日本
欺瞞・偽り・ごまかし
この花言葉には、色々な説や推測があります。
まず、鬼灯の大きくな袋に身が詰まってると思って、開けると中に小さい身が入っている事です。
つまり、
「期待したのに、中身が少ない!」
って感じです。
こういうのっていきてると結構ありますよね〜。ネットの写真は良かったのに、実際店に行くと…笑
なので、「騙された!」→「偽り、欺瞞」などの花言葉になったという考え方。
それと同じく、鬼灯の「小さい実を大きく見せるように見た目を偽ってる様にに見える」こととも考えられます。
ちなみに、西洋での「ごまかし」は、さくらんぼと鬼灯なら見た目が似ている事から、この花言葉になったと言われているんですよ。
「ラッキー、サクランボだ!」
と思ったのにって考えると、たしかに騙された気になってしまいます。笑
まぁ、実際に鬼灯とさくらんぼって、全然いてないと思うのは私だけじゃないですよね?

不貞・浮気・偽りの恋
この恋愛に関する花言葉は、先ほどの由来を恋愛に当てはめただけだと思います。
花言葉の文化って、恋愛と強く関係しているので、「偽りや欺瞞」を恋愛に変換して、「浮気・偽りの恋」と昼ドラチックな花言葉になったんじゃ無いでしょうか。
半信半疑・不思議
この花言葉は、鬼灯には毒が含まれてるけど、薬にも使われていることから「半信半疑」。
つまり、
「どっちなんだい!」
って気持ちの表れも考えられます。また、不思議という花言葉もこの特徴が由来かもしれませんね。
毒なのに薬って不思議ですから。
心の平安
これも先ほどの、薬として利用されていることが関係していると考えられています。
薬があるだけで安心感ってありますからね。
以上が、鬼灯の花言葉で由来と言われているものです。
これで「なんで怖い花言葉が付けられているのか?」に関して、少しスッキリしたんじゃないでしょうか。
それに花言葉の由来を知っておくだけで、その花の特徴がある程度わかるっていうのも面白い。なので、花言葉とセットで由来を覚えておくだけで花の知識は結構上がります!
花言葉の由来で鬼灯のことはある程度わかったともいます。
実は、この鬼灯って結構昔から日本で認知されていて、平安時代から書物に名前が残っているくらい身近な花だったんですよ。
昔は「鬼灯って字じゃない」って話もありますからね~。
せっかくなので次は、鬼灯の名前の由来と日本文化との関係について掘り上げて、お伝えいきたいと思います。
鬼灯の花名の由来と日本文化

鬼灯という名前の由来には諸説あります。
- 遊んでいる子供の赤く染まる頰から「頰突き」
- カメムシ(ホホ)が、付きやすい植物だから「ホホツキ」
などが名前の由来として有名な話です。
鬼灯が出てくる文献としては、あの有名な「古事記」が最も古い様です。
その内容としては、首が8つある八岐大蛇(ヤマタノオロチ)の赤い目の事を鬼灯と表されて、記述されているみたいです。
ただ、その時は「アカカガチ」と表記されていたらしいんですよ。
他にも平安時代に、日本最古の「本草和名」という薬に関する本でも登場しています。
そこでも名前は鬼灯ではなく、「酸漿(さんしょう)」という名前だった。
どうですかー?
鬼灯って日本の歴史的にも、結構馴染み深い植物という事なんですよ。
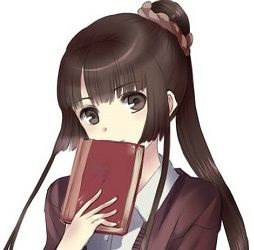 コトハちゃん
コトハちゃん
 コト助くん
コト助くん
鬼灯の花言葉と由来~まとめ~
 コト助くん
コト助くん
- 心の平安
- 不思議
- 自然美
- 私を誘ってください
- 偽り
- ごまかし(deception)
- 欺瞞(ぎまん)
- 半信半疑
- 偽りの恋
- 浮気
- 不貞
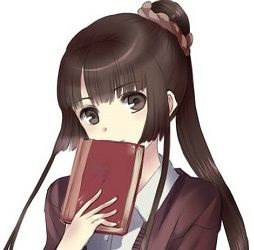 コトハちゃん
コトハちゃん
 コト助くん
コト助くん
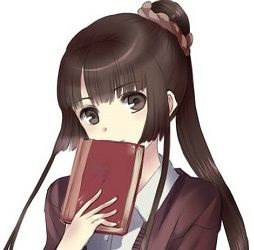 コトハちゃん
コトハちゃん
 コト助くん
コト助くん
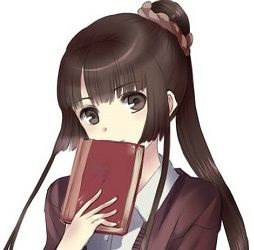 コトハちゃん
コトハちゃん


